今回両国駅の駅前のランドマークともいえる建築、東京都江戸東京博物館を訪れてきましたのでその模様をレポートしたいと思います。
【自己紹介】
・建築好きのやま菜と申します。
・今までに約5000件の建築を巡った建築トリッパー
・今日も素敵建築を求めて東奔西走
【この記事で分かること】
・江戸東京博物館を実際に訪れたレポートを写真と文字で解説
・江戸東京博物館の基本情報やアクセス方法、訪れる際のポイント
・江戸東京博物館の建築的な見どころや注目ポイント
東京都江戸東京博物館は、江戸東京の歴史と文化をふりかえり、その文化の保存と継承を目的に両国駅前に建てられた博物館です。
常設展示室では、約400年間に及ぶ江戸東京の歴史を実物資料や復元模型等をふんだんに使った展示の他、話題の企画展をいくつも企画する東京を代表する博物館です。

江戸東京博物館はバブル末期の1993年に完成し、その建築は日本を代表する建築家である菊竹清訓(きくたけ きよのり)氏が手掛けました。
菊竹氏といえば、都市と共に新陳代謝していく建築・都市像を提唱したメタボリズム(新陳代謝)運動の主要メンバーでもありましたが、この江戸東京博物館もメタボリズムの影響が色濃く反映されています。
メタボリズム建築といえば、このブログでも静岡新聞・静岡放送東京支社(設計:丹下健三/1967年)や中銀カプセルタワー(設計:黒川紀章/1972年)などを取り上げましたが、この江戸東京博物館はメタボリズム建築の中でも最も後年の時期に建てられた建築です。
関連記事
・丹下健三の静岡新聞・静岡放送ビルは銀座に残された1本の樹だった【東京銀座】
・メタボリズムの傑作!中銀カプセルタワーを外観から内部まで徹底レポート【東京銀座】
江戸東京博物館の建物の構成を見てみると、建物下部は特別展示室や運営諸室を設け、中間部のピロティを挟んで上部に常設展示室や収蔵庫、図書館が配置されています。
4本の巨大な大柱と2本の大梁のメガストラクチャーで支え、その他のサブストラクチャーの部分は時代の変化に応じて可変できるような構成です。

巨体な足で支えられた建物は高床式の倉の様な見た目です。
前回紹介した横須賀美術は江戸東京博物館は真逆の建築でいわは竪穴式といえるような美術館でした。
一方で今回の建物の設計者の菊竹清訓氏は高床式の建築家でもあり、両者を比較してみてみると面白いです。
幾度となく自然災害や戦争の惨禍に見舞われてきた江戸・東京における文化の収蔵・発信施設を考えた末に、4本脚で両国の地に鎮座する巨大生物のような建築が出来上がりました。

また、巨大生物のお腹の部分である巨大なピロティは、防災広場としての機能も持っています。
バブル期に建てられ建築家磯崎新から「東京5大粗大ごみ」と評され物議を醸した建築ですが、何があってもそこにあり続け、人々の居場所になるという意思を感じます。
ちなみに江戸東京博物館の高さは江戸城の天守閣と同じ約62mとなっています。
この江戸城の天守閣を参照したということも、どう見ても天守閣を想起できないなどの批判が多数あって、議論を呼びました。


実際どう感じるかは、見る人やタイミングによって変わってくると思いますが、もはや両国のランドマークとして多くの人に認知されて、親しまれていることは間違いありません。
博物館の展示だけでなく建築見学にもおススメの建築ですので、気になった人は是非一度トリップしてみて下さい。
ちなみに施設の老朽化に伴う大規模改修工事の為2022年の4月から2025年まで長期の休館予定となっていますので、訪れるなら早めがおススメです。
■まとめ
・4本の大柱と2本の大梁のメガストラクチャーで支え、フレキシブルな展示空間を目指したメタボリズム建築
・災害対策としての高床とピロティは、高床式の建築家である菊竹清訓氏の思想が最もよく表れた実例

【読むだけで建築について詳しくなれるイチオシの漫画】
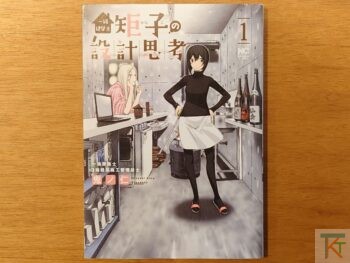
実際に一級建築士の資格を持つ人気R18漫画家が描く、唯一無二の建築漫画が話題になっています。
話ごとに建築のデザインはもちろん、法規や構造、施工や不動産に渡って幅広く扱っていて、建築好きなら毎回ワクワクしながら読めて、建築の知識も吸収できる超おススメ漫画です
>Amazonで詳細が読めます
また、当ブログでも漫画のレポートと、漫画と舞台となった亀戸の建築巡りについて紹介していますので、是非併せてご覧ください。
関連記事
・建築本「一級建築士矩子の設計思考」がスゴい!話題の本格建築漫画をレポート
2025年4月17日には「一級建築士矩子の設計思考」第4巻が発売になりましたので、是非チェックしてみて下さいね。
江戸東京博物館
設計:菊竹清訓
所在地:東京都墨田区横網1-4-1
アクセス:両国駅より徒歩約3分
竣工:1993年
開館時間:9:30~17:30(土曜日 9:30~19:30)
休館日:月曜
常設展観覧料:
一般 600円
大学生・専門学校生 480円
高校生・中学生・65歳以上 300円
公式HP:https://www.edo-tokyo-museum.or.jp/
備考:現在設備機器更新等の大規模改修工事を行うため2025年度まで休館中
【おススメの建築本を紹介】
建築に興味のある人へのイチオシ書籍!本当に楽しくてわかりやすくて、建築の魅力を存分に感じつつ様々な知識も楽しく知ることができます。

>Amazonから詳細の内容を見れるので、是非チェックしてみて下さいね。
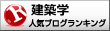 建築学ランキング
建築学ランキング↑建築系のブログランキング。よければクリックして応援してもらえると嬉しいです。
建築やデザイン好きな人は、他にも面白いブログや参考になるブログがいっぱいあるので是非見てみてください^^




